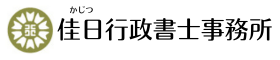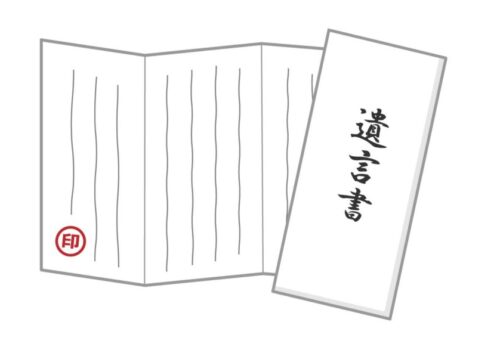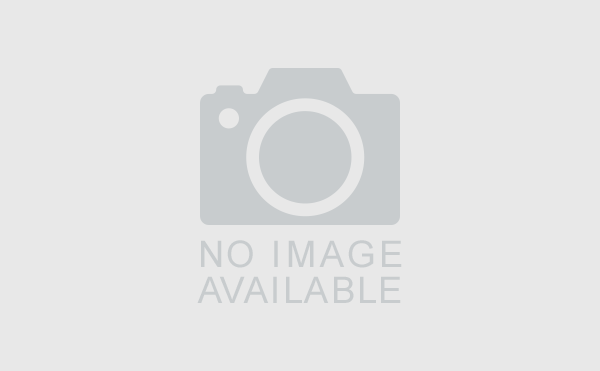遺言書を書く前に知っておきたい、「遺留分」とは?
「自分の財産は自分の好きなように遺したい」そう考える方は多いでしょう。遺言書は、あなたの想いを法的に実現するための大切な手段です。
しかし、遺言書を作成する前に必ず知っておきたい重要なキーワードがあります。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、後々相続人間で争いが起こる可能性も。
せっかく作成した遺言書が、かえって家族を困らせてしまうかもしれません。
この記事では、遺言書を書こうと考えているあなたに向けて、遺留分の基本をやさしく解説します。
遺留分を正しく理解することで、あなたの想いを尊重しつつ、円満な相続を実現するための遺言書作成に繋がるはずです。
遺留分とは?遺言書の自由を制限するルール
「遺留分って、遺言書があってももらえるお金のこと?」
簡単に言うと、その通りです。遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、”配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)”といった一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。
遺言書は、民法で認められた権利であり、原則として誰に何を相続させるかを自由に決めることができます。
しかし、この自由な遺言によって、残された家族の生活が困窮してしまうような事態を防ぐために、遺留分という制度が存在します。
つまり、遺言書の自由を一部制限することで、相続人間の公平性を保ち、残された家族の生活を保障する役割があるのです。
遺留分が認められる相続人は?誰に配慮が必要か
遺言書を作成する上で、特に遺留分に配慮が必要な相続人は以下の通りです。
- 配偶者: 常に遺留分が認められます。
- 子: 実子、養子、非嫡出子に関わらず、遺留分が認められます。子が亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として遺留分を承継します。
- 直系尊属: 親や祖父母など、被相続人の直系の先祖です。ただし、子やその代襲相続人がいる場合は、直系尊属には遺留分は認められません。
兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、遺言書で兄弟姉妹に一切財産を相続させないとしても、遺留分侵害の問題は生じません。
遺言書を作成する際には、これらの遺留分権利者の存在を念頭に置き、遺産の配分を検討する必要があります。
遺留分の割合は?遺言書で考慮すべき最低限の取り分
では、具体的にどれくらいの割合が遺留分として保障されているのでしょうか。遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 遺留分の総額:法定相続分の1/2または1/3です。相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外の場合は1/2となります。
- 各相続人の遺留分割合: 上記の遺留分の総額を、法定相続人の数に応じてさらに細かく計算します。
- 例1:配偶者と子1人の場合
- 遺留分の総額:遺産の2分の1
- 配偶者の遺留分:遺産の2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子の遺留分:遺産の2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 例2:子が2人の場合
- 遺留分の総額:遺産の2分の1
- 各子の遺留分:遺産の2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 例1:配偶者と子1人の場合
遺言書で特定の相続人に多くの財産を遺したい場合でも、これらの遺留分の割合を考慮する必要があります。
もし、遺言書の内容がこの最低限の取り分を下回る場合、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」が行われる可能性があります。
【遺留分侵害額請求】とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言書や生前贈与によって自己の遺留分が侵害された相続人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利のことです。
例えば、遺言書で全く遺産を受け取れなかった相続人や、遺留分を下回る額しか指定されなかった相続人は、遺産を多く受け取った人に対して、不足分の金銭を請求することができます。
この請求は、原則として遺留分を侵害する事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
これは、権利ですので請求しない選択もできます。
遺留分を計算する際の注意点:【特別受益】とは?
遺留分を計算する際には、「特別受益(とくべつじゅえき)」という考え方も重要になります。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。具体的には、以下のようなものが該当します。
- 結婚や養子縁組のための費用
- 生計の資本としての贈与(事業資金など)
- 住宅購入費用
このような特別受益があった場合、遺留分を計算する際には、その特別受益の額を相続財産に持ち戻して計算することがあります。
これにより、生前に多くの利益を得ていた相続人の遺留分が調整され、相続人間の公平が図られます。
遺言書を作成する際にも、特別受益を受けた相続人がいる場合は、その点を考慮して財産配分を検討することが望ましいでしょう。
遺留分を侵害する遺言書とは?具体的なケースで解説
具体的にどのような遺言書が遺留分を侵害する可能性があるのでしょうか。
- ケース1:特定の相続人に全ての財産を相続させる遺言書例えば、「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成した場合、配偶者や他の子には遺留分が保障されています。これらの相続人は、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
- ケース2:相続人以外の人に多くの財産を遺贈する遺言書例えば、「お世話になった第三者に〇〇円を遺贈する」という内容の遺言書を作成した場合、その遺贈によって相続人の遺留分が不足する可能性があります。この場合も、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた第三者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
- ケース3:生前贈与によって特定の相続人の遺留分が大きく減っている場合特定の相続人に多額の生前贈与を行っていた場合、遺言書で他の相続人に財産を残しても、生前贈与と遺言による相続財産を合計したものが遺留分を下回ることがあります。この場合も、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
遺留分を侵害する遺言書を作成してしまうと、相続発生後に相続人間で感情的な対立が生じ、紛争が長期化する恐れがあります。
遺留分に配慮した遺言書を作成するには?
では、遺留分に配慮しながら、自分の想いを実現できる遺言書を作成するにはどうすれば良いのでしょうか。
- 各相続人の遺留分を考慮した財産配分にする
遺留分の割合を念頭に置き、各相続人に最低限の財産が承継されるように配慮しましょう。 - 特定の相続人に多くの財産を遺したい場合は、その理由を遺言書に明確に記載する(付言事項)
なぜ特定の相続人に多くの財産を遺したいのか、感謝の気持ちや相続への想いを「付言事項」として遺言書に記載することで、他の相続人の理解を得やすくなることがあります。
付言事項には法的拘束力はありませんが、相続人間の感情的なわだかまりを軽減する効果が期待できます。 - 生前贈与を活用する場合は、遺留分の計算に入れる必要があることを理解しておく
生前贈与は、相続開始前10年以内のものや、特別受益に当たるものは遺留分を計算する際の基礎となる財産に含まれます。
生前贈与を行う際は、将来の遺留分への影響も考慮しておきましょう。 - 専門家(行政書士など)に相談しながら作成する
遺留分は複雑な問題も多く、ご自身の状況に合わせてどのように遺言書を作成すれば良いか悩むこともあるでしょう。
相続に詳しい専門家(行政書士、弁護士など)に相談することで、遺留分に配慮した、より確実な遺言書を作成することができます。
遺留分についてもっと詳しく知りたい方へ
遺留分は、遺言書作成において非常に重要なポイントです。
ご自身の状況に合わせて、どのように遺言書を作成すれば良いか、また遺留分についてもっと詳しく知りたいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続に関する様々な疑問や不安に対し、専門的な知識と丁寧な対応でお応えいたします。
- 遺留分を踏まえた最適な遺言書作成のアドバイス
- 相続手続きに関するご相談
- お客様の想いを実現するためのサポート
初回無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください
【お問い合わせ先】奈良市の佳日行政書士事務所
・事務所所在地:奈良県奈良市あやめ池北一丁目25番37号
事務所とご自宅がお近くでしたら、ご訪問も可能です。
訪問可能地域:奈良市・大和郡山市・生駒市・斑鳩町・木津川市 その他ご相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。0742-55-4376受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください
あなたにとって最善の遺言書作成をサポートさせていただきます。
まとめ:遺留分を理解して、後悔のない遺言書を
遺言書は、あなたの人生の集大成とも言える大切なメッセージです。
遺留分という制度を正しく理解し、それに配慮した遺言書を作成することで、あなたの想いをしっかりと家族に伝え、将来の相続争いを防ぐことができます。
後悔のない遺言書を作成するために、まずは遺留分についてしっかりと理解しておきましょう。
そして、少しでも不安なことや疑問点があれば、迷わず専門家にご相談ください。